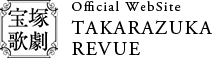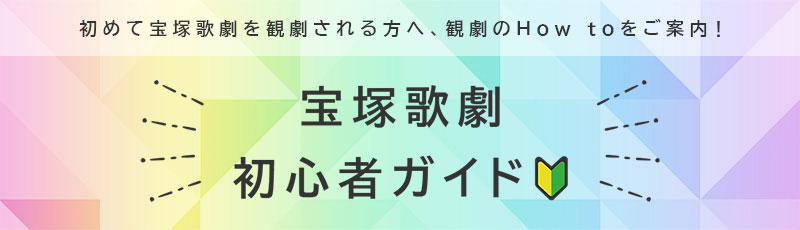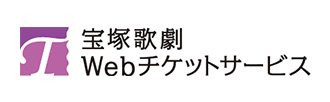演出家コメント
柴田侑宏(『新源氏物語』脚本)

『新源氏物語』について
「源氏物語」は、一条天皇の頃、紫式部によって書かれた日本最古の長編小説。当時の宮廷を舞台にした54帖(章)の大ロマンは、主人公の光り輝くような貴公子“光”の恋の種々相(しゅじゅそう)、数奇な運命、登場人物の多さで、読者を惹きつけて飽きさせない、スケールをもった作品である。
この平安期の古文による大長編の現代語訳は有名作家が何人か試みておられるが、当時、田辺聖子先生の「新源氏物語」が現代人の理解にたいへん近いところにあるのではと、時の理事長、市川安男氏が興された企画と聞いている。
この度の公演は、この『新源氏物語』の3度目の公演となる。初演は2部25場の長編で、2度目の時から2本立ての一編として上演されるため、縮尺やカットが行われた。
『新源氏物語』の秘められたもの
(紫の上を妻としていた頃、光源氏は、宮中で大切な仕事を担っていた。帝の補佐役であり、皇太子の後見としても重用されていた。)
光源氏は、自分の子供かもしれない皇太子を導き、帝として教育せねばならない。
この重い仕事の合間に、事件が起きる。
世を儚み出家する兄・朱雀帝の頼みで、女三の宮という女性を正式の妻として迎えることとなった源氏。仕方なく受け入れるものの、正式の妻ではない紫の上にどう言い訳すべきかと悩む。
この結婚の結末に、源氏を打ちのめすことが起きる!
息子の友達、柏木が密かに女三宮と通じており、・・・その二人の子を、三宮が出産したのだ!
慄然(りつぜん)とする光源氏。 “父上、あなたは私を赦さなかった!!”
視線の定まらない源氏に、惟光の声が「お車の支度が整いました。」
「よし、宮中へ参るぞ!」
『新源氏物語』のあらまし
当時の宮廷の中で“光の君“と誰もが敬愛していた帝の第二皇子には大きな恋の悩みがあった。その相手は、誰あろう、光の母、桐壺の更衣の後添えに娶った藤壺の女御が母と似ているという噂から、母恋しさがいつの間にか恋している自分に気がつくのだった。
その年の七夕の夜、宿直(とのい)仲間の青年たちと別れて藤壺を訪れ、無理やり王命婦(おうのみょうぶ)に案内させ、藤壺に恋の告白・・・そして、抱きすくめるのだった。
藤壺もまた、逃れようとするが、光に心を引かれた自分を覚って、抵抗の力が萎えていく。
天にも昇る心地の光だったが、これまでに宮廷の内外に何人も恋人がいる生活があり、この所行は、藤壺に会うことができなかったせいであると彼自身は思っていた。
そのうちの一人で、身分も高いがそれ以上に権(けん)高(だか)い女性に、六条御息所という女性がいた。この人も母に似ていた。持ち重りのする女性で、できれば少々時をあけて訪問したいと思っていた。それを、ぴったり供についていた惟光(これみつ)は、手に取るようにわかり、苦笑することがあった。
ところで、光源氏はこの時代の常に習い、16歳の頃、左大臣の息女葵の上と結婚し、一子(夕霧)を設けていたのだった。
だがこの葵との気持ちが寄り添わず、味気ない夫婦生活だったのを惟光も知っている。
事件が起こった。
その年の葵祭りの日、貴公子たちが美々しく着飾って都大路を闊歩するというので、大勢の見物客が出ていた。六条御息所も供を従え美しい車に乗って出かけたが、運悪く葵の上の車も乱暴な従者たちに囲まれて大路に出ていた。
そして、両者は目ざとく相手を認め合い、従者たちの喧嘩が始まり、挙句に御息所の車が壊され、後ろにどかされてしまった。
御息所は這々(ほうぼう)の体(てい)で、屋敷へ帰った。
その夜のうち、御息所の生霊に襲われ、葵は高熱を発して倒れてしまった。そして、駆けつけた源氏や左大臣たちに囲まれて息を引き取った。
心残る思いをし、北山を散策していた源氏の前に、愛らしい女(め)の童(わらわ)が現れる。この少女(若紫)がまた藤壺に似ている面影を持っていた。
惟光に調べさせ、家と身元をつかんだ光は、乗り込んで親代わりの尼(あま)御前(ごぜ)に名乗り、自分が養父になると頼むが、断られる。
その時源氏のとった行動には、惟光も驚くばかり。黙って断りもなく、眠っている若紫を惟光に負わせて帰ってきてしまうのである。
この無軌道な話の成り行きをしばらく追い続けて・・・舞台は若紫の成人ぶりを描くことになる。
ほんのねんねの十(とお)ばかりの少女が成人するまでを見せて行く。教養を身につけ、美しく成長し、みるみる源氏の横に並んでも不足ない女性となり、紫の上と名づけられ、源氏の妻となるわけである。(しかし親元を世間に知らせられないので正式の夫人とはなっていない。)
大野拓史(『新源氏物語』演出)

作品の見所、花組の魅力について
「平安王朝の理想の貴公子というだけではなく、その深い心ざまとともに、行動的で果断な決断力もある、情熱の青年」(再演時のプログラムより)
それが、田辺聖子先生の原作を基に、柴田侑宏先生が描かれた、宝塚歌劇の光源氏の姿です。
主演の明日海りおは、かなり「情熱」派の役者です。わざわざアピールしてみせる事は無いので、そうした印象を持たない方もいらっしゃると思いますが、以前から稽古場で感じてきた明日海りおの「情熱」を、熱さを、どの様にお見せ出来るのか。それこそが作品の成否を決めるのではないかと思い、取り組もうと考えております。
光源氏=情熱の青年=明日海りおの姿を、お楽しみに。
お客様へのメッセージ
今回、再々演とはいえ、かなり柴田侑宏先生が脚本に手を入れておられます。
作品の質の向上を、あくまでも追求し続ける姿勢には、改めて頭の下がる思いですが、けれどもそれは、舞台人として当たり前の事なのでしょう。
舞台は、その都度つくりあげていくものです。本来、舞台に「再演」などと言う概念は、不要のものであるのかもしれません。
ですから、明日海りおが、花乃まりあが、花組や専科の出演者たちが、どのように『新源氏物語』という作品をつくりあげたのか。その成果をこそ、ご覧頂ければと考えております。
中村一徳(『Melodia -熱く美しき旋律-』作・演出)

作品のテーマと見どころ
明日海りお率いる新生花組の宝塚大劇場作品は、1本立て大作ミュージカル『エリザベート』、オリジナル作品『カリスタの海に抱かれて』『宝塚幻想曲(タカラヅカ ファンタジア)』の芝居・ショー2本立てともに、非常に高い評価を受けました。現体制の花組となり3度目の大劇場公演となる今作、勢いにのった花組の魅力と実力そしてパワーを証明するにふさわしい、絢爛なレビューショーをお届けしたいと思います。
ラテンのリズムのプロローグからスーツスタイルのJAZZのシーン、黄金郷の場面からスペインのフェスタへ展開し、クライマックスに向けて、大階段を使った黒燕尾姿の男役のダンスナンバー、愛溢れる大人のトップコンビのデュエットダンスへと、躍動的なシーンが続きます。
テーマである美しいメロディと熱きリズムに乗せた、花組の若さ溢れる魅力をお楽しみください。
公演への意気込みとお客様へのメッセージ
先述の宝塚大劇場公演の作品のみならず、全国各地、そして海外公演となる台湾においても、どの作品も、今の花組の充実ぶりを十分窺わせるものでした。この花組の魅力をこれまで以上に引き出しお伝えすることは大変大きなプレッシャーですが、花組生一人ひとりが非常に個性溢れ、また魅力的であることに、作者として大いなる期待を寄せています。
名作『新源氏物語』の究極の美しい物語、舞台に負けじと意欲的にお届けいたします、グランド・レビュー『Melodia-熱く美しき旋律-』を、どうぞよろしくお願いいたします。