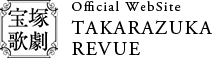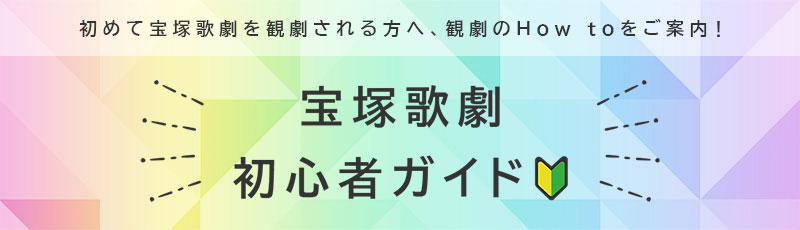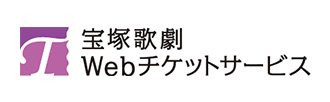演出家 原田諒が語る
ミュージカル『ピガール狂騒曲』〜シェイクスピア原作「十二夜」より〜の見どころ<前編>
宝塚歌劇ならではの様式美を受け継ぎながら、登場人物たちが“物語に息づく”リアリズムをどこまで表現出来るのか——その果敢なチャレンジの積み重ねは、演出家・原田諒の評価を着実に高めてきた。活躍の場はいまや宝塚歌劇にとどまらず、日本の演劇界においても注目の存在である。
今回手掛ける大劇場作品『ピガール狂騒曲』は、シェイクスピア喜劇の最高傑作とも謳われる「十二夜」をベースに、ベル・エポック華やかなりし時代のフランスに舞台を移し、史実と創作を交えて描かれる快活な祝祭劇。充実期を迎えた月組とのタッグに期待が高まる。
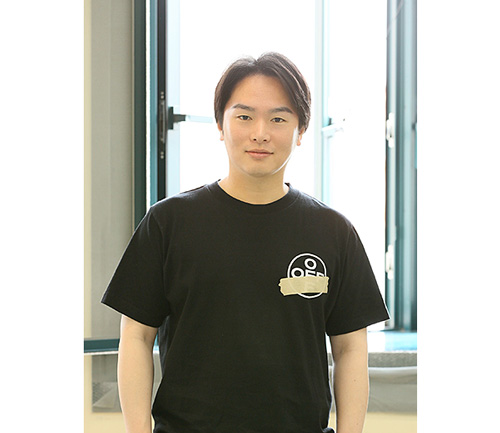
今作『ピガール狂騒曲』の制作意図をお聞かせください。
昨年の『チェ・ゲバラ』に続いて月組公演を担当させていただきますが、今回は初舞台生も迎えた大劇場公演ということもあり、キューバ革命を題材にした前作とはタッチを変えて、春の宝塚(当初4月25日初日予定)に似合う軽やかで心が浮き立つような作品にしようと思いました。珠城りょう率いる今の月組は明るく、バラエティ豊かなメンバーが揃っていますので、以前から舞台化してみたかったベル・エポック(輝かしき時代)と言われた世紀末パリを舞台にした喜劇は面白いのではないかと考えました。
この時代はエッフェル塔やグラン・パレなど、アール・ヌーボーの意匠を凝らした鉄とガラスの建造物が出現し、メトロが走り出した20世紀の夜明けです。歴史に名を残す芸術家たちが、世界中からパリに集い、文化が花開いた華やかなりし時代の熱狂と興奮、そして個性豊かな人物たちは、まるでシェイクスピア喜劇とその登場人物のようでもあり、今の月組の面々と重なるところでもあります。ベル・エポックの時代に実在した人物、実在したかもしれない架空の人物、虚実を織り交ぜた祝祭劇が創れたらと思いました。
作品の舞台となるピガールは、どのようなところでしょうか。
「ピガール」はパリ北部、モンマルトルの丘の麓にあるエリアです。現在も多くの人々が訪れるムーラン・ルージュをはじめとしたミュージック・ホールが軒を連ねる歓楽街として発展しました。洗濯船に代表されるようなアトリエも多く、のちにパブロ・ピカソやモーリス・ユトリロなど、後世に名を残す芸術家が集ったのもこの地です。今回の舞台であるムーラン・ルージュといえば、踊り子たちを描いたトゥールーズ・ロートレックを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。今回の作品を創るにあたって、ロートレックがモデルにしたジャンヌ・アヴリルという踊り子や、本作のヒロインであり実際にムーラン・ルージュの舞台に立った女流作家、シドニー=ガブリエル・コレットの半生からもインスパイアを受け、想像を膨らませた部分が大きいですね。
実際にピガールを訪れたことはありますか?
これまでにも何度か足を運んだことがあります。決して治安のいいエリアではありませんが、ベル・エポックに作られた建物が今も残り、歓楽街としての華やかさと下町ならではの雑多な雰囲気は、当時の空気を今に伝えてくれているように思います。ウディ・アレン監督の映画「ミッドナイト・イン・パリ」で、1920年代のパリに憧れる主人公がタイムスリップし、そこでベル・エポック期のパリに憧れる女性に出会うというエピソードがありましたが、ピガールやモンマルトルの裏街を歩いていると、本当にあの映画のように遠い時代に迷い込んでしまうような気分になりますね。シャンゼリゼとはまた違うパリの魅力が感じられ、私にとって創作意欲を刺激される街でもあり、以前から彼の地を舞台にした作品を創ってみたいと考えていました。
今作ではシェイクスピアの喜劇「十二夜」の舞台をピガールに移して展開されますが、異なる点や共通点は?
「十二夜」はシェイクスピアの三大喜劇の一つにも数えられる作品ですから、ご存知の方も沢山いらっしゃると思います。船の難破で生き別れになった双子の兄妹、セバスチャンと、男装することとなった妹のヴァイオラを軸に、ヴァイオラが仕えるオーシーノ公爵、彼の想い人である伯爵令嬢オリヴィアの不思議な三角関係が展開される物語ですが、今作では「十二夜」の人間関係に固執するのではなく、あくまでもその枠組みを借りたオリジナル作品としての『ピガール狂騒曲』を創り上げたいと考えています。ですから、メインとなる四人以外にも、「十二夜」に登場するキャラクターにリンクするような様々な人物が登場しますが、「十二夜」では一つの役が担う役割を複数の役に振り分けたり、逆に二人の人物の役を一役にミックスさせたりしています。ほかにも原作にはない役どころも出てきますので、「十二夜」との違いや共通点を見つけてお楽しみいただければと思います。
ミュージカル『ピガール狂騒曲』〜シェイクスピア原作「十二夜」より〜の見どころ<後編>
インタビュー<後編>では、珠城りょうら出演者や、月組の魅力を中心に話を聞いた。

珠城りょうは、今回ジャックとヴィクトールの二役に扮しますが。
ここしばらく月組は、海外ミュージカル作品や名作の再演が続いていましたので、久々のオリジナル作品として、充実期を迎えた珠城りょうだからこそ出来る役、そしてこれまでの彼女のレパートリーにはなかった役どころに挑戦してもらい、彼女の新たな一面をご覧いただければと思います。今回は原作の「十二夜」においてはヴァイオラにあたるジャック=ジャンヌと、セバスチャンにあたるヴィクトールの二役に挑戦してもらっています。異なる性格の兄妹の演じ分け、早替りが見どころの一つですが、実に鮮やかに演じてくれています。彼女の明るさと大らかさ、そして真面目で真摯な姿勢がうまく投影できればと思い創った役ですので、稽古を重ねるごとに手応えを感じています。3月に稽古が始まり、途中4ヶ月近くの稽古中断期間を挟んで、誰もが経験したことのない困難な稽古期間を経ましたが、いつにも増して明るく真摯に皆を引っ張ってゆく姿には、組を率いるトップスターとしての風格と頼もしさを感じずにはおられませんでした。そんな彼女が月組のトップとして存在し、組を牽引してくれたからこそ、こうして初日を迎えられたと心から感謝しています。
ガブリエル役の美園さくらについては。
彼女の演じるガブリエル・コレットは実在の人物で、夫であるウィリー(アンリ・ゴーティエ=ヴィラール)のゴーストライターとして「クロディーヌ」という小説を書きました。彼女はのちに女流作家として身を立てますが、離婚してしばらくの間、ムーラン・ルージュの舞台に立ったという記録があるんですね。実際は生活苦のためだったとも言われていますが、自らの名で作品を出せる作家になれるほどの文才のある元作家夫人が、キャバレーの舞台に立つというエピソードはとても興味深く、そのエピソードからイメージを膨らませて今回の作品の軸を作ったところもあります。ベル・エポックは女性の解放の時代でもありました。体を締め付けていたコルセットを外し、新しいスタイルの洋服で活動の自由を得、世に出て行った女性たちの先駆けがこのガブリエルであると思うんですね。ガブリエルの強い意志と女性としてのチャーミングさ、そして人間としてのユニークさは美園に通じるところでもありますから、彼女自身とガブリエルがうまく重なり、魅力的なキャラクターになるよう、日々頑張ってくれています。
そのほか、今の月組の布陣についてはいかがでしょうか。
月城かなとを筆頭に、鳳月杏、暁千星、風間柚乃、そして娘役も海乃美月や天紫珠李をはじめ個性豊かで頼もしい面々です。特に月城は怪我のため『チェ・ゲバラ』の出演が叶いませんでしたので、私にとっては『瑠璃色の刻(とき)』(2017年)以来の再会となりましたが、男役としての成長ぶりに目を瞠る毎日です。そんな彼女と久しぶりに芝居を創れるのが嬉しいですね。今回はシャルル・ジドレールという、ムーラン・ルージュの少しエキセントリックな支配人を演じてもらっていますが、これまでの彼女のレパートリーにはあまりなかった色濃い、面白いものに作り上げてくれました。とにかく人材豊富な組ですから、出演者それぞれに個性的な役を演じてもらっています。一人ひとりの個性が役に投影出来るように、また新たな一面が開花するような面白い作品にしたいと思って稽古に臨みました。
今回は芝居のあとにフィナーレが付くスタイルでの公演となりますが。
昨今、様々なジャンルの作品が宝塚歌劇の舞台でも掛かるようになりましたが、改めて宝塚らしさとは何かを考えたときに、舞台美術、音楽、衣装、振付、すべてにおいて宝塚歌劇は「品」が必要だと痛感しています。たとえば舞台で使われるピンク色ひとつ取っても、その彩度と使い方の加減によって上品にも下品にもなりますよね。昭和初期に岸田辰彌や白井鐵造といった演出家の大先輩たちがパリへ留学し、それこそムーラン・ルージュやカジノ・ド・パリなど、当時全盛を誇ったミュージック・ホールでのレビューを学び、女性性を売るバーレスクだった部分を転化し、清く正しく美しく、甘く、品良く昇華させていったのが宝塚のレビューです。今回は本編が、パリが最もパリらしかった時代が舞台ですから、フィナーレも白井調のパリ・レビュー風のものにしました。ですから舞台美術や衣装、照明に使う色彩・配色バランスにもいつも以上に気を使いましたし、音楽もすべてシャンソンの名曲で構成しました。時代を超えて生き続ける音楽の良さは、やはりメロディーにあると思います。目新しさだけを追って新しい音楽を使うより、センスとアレンジ次第で百年前の流行曲も現代のヒットチャートより斬新なものに出来ると思います。宝塚ならではの品の良さと美しさ、そして贅沢な夢に酔っていただければ嬉しいです。
また、第106期初舞台生の公演でもあります。
私が初舞台生を迎える大劇場公演を担当するのは8年ぶり、大劇場デビュー作の『華やかなりし日々』(2012年宙組)以来です。106期生はこの春に初舞台を踏むはずでしたが、稽古が中断し5ヶ月遅れの初舞台となりました。稽古中断期間中、この先どうなるのかという不安も大いにあったと思いますし、歌劇団の一員になったものの未だ舞台を踏めていないもどかしさもあったと思います。しかし、それを打破するだけの高いモチベーションを維持して本当によく頑張ってくれました。今日の初日は生涯忘れられない一日になったと思います。彼女たちの待ちに待ったタカラジェンヌとしての門出に大きな拍手を贈りたいです。
コロナ禍による公演中止を経てようやく初日の幕が開いた今、お客様へのメッセージをお願いします。
5ヶ月遅れの初日となりましたが、誰一人欠けることなく、出演者・スタッフ全員が健康で元気に初日を迎えられたこと、そして大勢のお客様に観ていただけたことが本当に嬉しくありがたいです。我々演劇人は「開かない初日はない」と信じ、その言葉に励まされてきましたが、今回の新型コロナウイルスの蔓延によって世界中の多くの劇場で初日の幕が開かない事態になってしまいました。私自身、この月組公演もどうなるかと不安と焦燥を感じたことも事実です。長い自粛期間を経ての稽古再開は、出演者の安全を確保し、お客様に安心して観ていただくため、当初予定していた演出・振付プランを見直し、これまでの稽古のスタイルを変えた「新しい生活様式」の中での試行錯誤の毎日でしたが、稽古場にいる一人一人が前向きに、そしていつも以上に健康管理・衛生管理に注意しながら取り組んでくれました。同時に、世界中が見えない敵と戦い続けている中で、演劇の使命と存在意義はどこにあるのか、その役割を考える毎日でもありました。我々エンターテイメントの仕事は時に不要不急という言葉で括られてしまいがちですが、演劇には、宝塚には、薬では治せないものを治す力があると信じています。苦しい日常がまだまだ続きますが、せめて束の間の夢のひとときをお届けできるよう、明日からも出演者・スタッフ心ひとつに、そして気を引き締めて日々の舞台をつとめて参りたいと思います。
【プロフィール】
原田 諒
2003年宝塚歌劇団入団。バウ・ミュージカル『Je Chante(ジュ シャント) -終わりなき喝采-』(2010年宙組)で演出家デビュー。宝塚大劇場・東京宝塚劇場デビュー作の『華やかなりし日々』(2012年宙組)、20世紀を代表する報道写真家の半生を描いた『ロバート・キャパ 魂の記録』(2012年宙組)で、第20回読売演劇大賞 優秀演出家賞、「ミュージカル」誌における2012年ミュージカル・ベストテン演出家賞を受賞。その後も、高く評価される作品を続々と世に送り出し、2016年には自身初となる日本物レビュー『雪華抄(せっかしょう)』(花組)を発表。同年に作・演出を手掛けた『For the people -リンカーン 自由を求めた男-』(花組)で、第24回読売演劇大賞 優秀演出家賞・優秀作品賞を受賞。続く2017年『ベルリン、わが愛』(星組)、2018年、『ドクトル・ジバゴ』(星組)の脚本・演出に対して第43回菊田一夫演劇賞が贈られたことは記憶に新しい。昨年はオリジナルの軽妙な持ち味をさらにブラッシュアップさせたブロードウェイ・ミュージカルの名作『20世紀号に乗って』(雪組)の宝塚歌劇版を手掛けた後、キューバ革命の指導者チェ・ゲバラの生き様を力強く描き出した骨太の人間ドラマ『チェ・ゲバラ』(月組)で守備範囲の広さを見せる。今年2月にはオペラ「椿姫」の演出に招聘され、外部作品でも新たなジャンルを開拓。今、最も注目を集める実力派若手演出家の一人である。