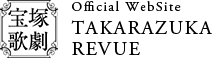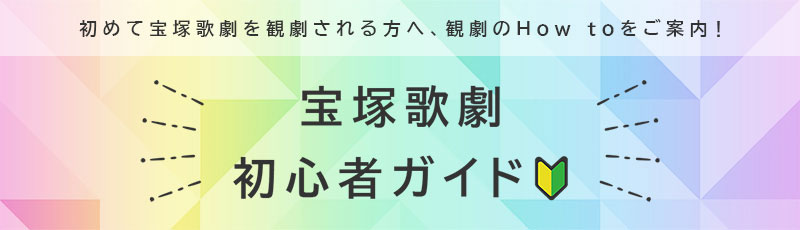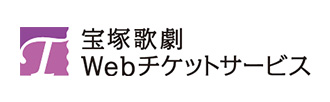浅田次郎氏×田渕大輔 対談
宝塚歌劇宙組公演として上演される『王妃の館 -Château de la Reine-』の原作者・浅田次郎氏と、脚本・演出を手掛ける演出家・田渕大輔に話を聞いた。舞台化への想いから浅田氏の創作秘話まで、さまざまな話が飛び出した。
宝塚歌劇での舞台化にふさわしい華やかな小説

——「王妃の館」を宝塚歌劇で舞台化、というお話をお聞きになったときの率直なご感想は?
浅田:思いがけなかったですね。タカラヅカでの舞台化、というのは考えもしていませんでしたが、とても嬉しかったです。
田渕:「王妃の館」との出合いは、浅田先生が連載されているエッセイがきっかけでした。いつも楽しみに拝読しているのですが、ちょうどこの作品の映画化にあたって、「まさかこの『王妃の館』が映像化されるとは!」と書かれていたのを見て興味を抱きました。小説を拝読すると舞台の群像劇を観ているような感じで、もしこれを舞台化したらどうなるだろうと、漠然と思ったのが最初です。
浅田:そうだったんですね(笑)。僕はいつも小説のことしか考えていないので、映像化や舞台化は全く想定していません。特に「王妃の館」は小説家としての感覚では、一番映像にも舞台にもなりにくいと思っていました。ただ、宝塚歌劇で舞台化と聞いたときは、「それはしっくりくるな!」と感じました。
田渕:宝塚歌劇だから、というところはあると思います。
浅田:「王妃の館」は僕の小説のなかでもかなり華やかです。フランスのブルボン王朝が出てくるし、登場人物も多いので、宝塚歌劇に通ずる華やかさがありますね。
田渕:舞台化にあたっては上演時間のなかで、いかにテンポよくクライマックスへもっていけるかがカギになります。浅田先生が小説で描かれているテーマを失わずに、そして作品にある“愛”を大切に、宝塚歌劇の作品として色付けしていけたらと思っています。コメディのなかで語られる台詞だからこそ、より心に染みる部分があると感じるので、丁寧にアプローチし、原作の魅力を損なわないように心掛けたいと思います。
——コメディだからこそ描けるものがあるのでしょうか?
浅田:特別意識していることはありませんが、やはり笑いというのは考えて出てくるものではないんですね。笑いは即興じゃないと面白くない。だからこそ“お笑い小説”は難しいし、資質を問われます。コメディのセンスというのは、ダメな人は最初からダメなので。
田渕:(笑)。
浅田:これは努力して磨かれるものではなく天性のものです。だから田渕先生と宙組の皆さんが持っているコメディセンスを上手く出してくださったら、面白くなると思います。
ルイ14世の時代へ自然と導き、喜劇と悲劇を表現

——浅田先生は先日、宙組公演『エリザベート-愛と死の輪舞(ロンド)-』で宝塚歌劇を初めてご覧になられたそうですね。
浅田:タカラヅカの様式美、100年以上も続くなかで蓄積されたスタイルが踏襲されていることに、ものすごく感動しました。タカラヅカを知らない人は「なぜ最後に羽根を背負った人が大階段に登場するのか!?」などと思うわけです。でも、その“お定め事”がとても良かった。
田渕:ありがとうございます。
浅田:あらゆる芸術に言えますが、確立した様式や基礎がないと新しいものは創れないと思います。ただの前衛というのはあり得ない。やはりベースに古典的なものがあって、そこから新しいものを創っていくのが正しい芸術だと思っていますので、その観点からもタカラヅカに大変感動しました。
田渕:舞台を創る過程はアナログで、結構泥臭いところもあると思うのですが、その過程があるからこそ、様式美の大切さを信じて、皆が突き進む事が出来るのかなと。それをお客様に評価していただけるのは、本当に嬉しい限りです。
浅田:僕も小説家としては非常に古風なスタイルを持っています。いまだに畳に座って原稿用紙に万年筆で小説を書いているんですよ。
田渕:そうなのですか!
浅田:「王妃の館」も、そうやって書きました。僕は新しいやり方よりも昔からのスタイルを信じていますから、そういう僕の芸術観とタカラヅカは一致しました(笑)。
田渕:嬉しいお言葉です。
——浅田先生はパリがお好きで、ルイ14世に興味があるというのも、宝塚歌劇の世界観に通じるものがあるのかもしれませんね。
浅田:確かにそうですね(笑)。僕はルイ14世をコメディのなかで描きましたが、歴史的な事実の裏付けがあり、資料を色々と調べたうえでの僕の解釈があの人物なのです。自らコメディ・フランセーズを主宰しパトロンになっているわけだから、オカシイ人だったはずなんですよ。そう考えるとルイ14世の肖像画などが、全部ギャグに見えてくるわけです(笑)。
田渕:なるほど! ルイ14世の肖像画に描かれたあのカツラも(笑)。
浅田:そうです。青いタイツも(笑)。そう分析した結果、「王妃の館」のルイ14世が誕生しました。
田渕:劇中でどのようにルイ14世の時代へお客様を導き、物語を結末へともっていくかが、今一番大きな課題だと考えています。ただ奇をてらうのではなく、作品世界のために自然な形で解決できたらと考えていたので、いま浅田先生のお話を伺うことができてとても参考になりました。
浅田:ルイ14世はヴェルサイユ宮殿の「鏡の回廊」や庭園の造作を見てもわかる通り、自然を支配しようとしたのです。何でも人工的にしなければ気が済まないという感じがありますね。
田渕:支配欲がそれをもたらしたのですね。
浅田:あれは日本人の美学から言うと悪趣味にも見えるのですが、そこに僕はとても興味を持ちました。
田渕:ひとつお伺いしてもよろしいですか? ルイ14世はブルボン王朝時代の王のなかでも一番安泰な時代の王様というイメージもあると思います。創作の最初からルイ14世の人物像は浅田先生のなかにあったのでしょうか。
浅田:物語を書き始める前からありました。自然までも支配しようとする人間の悲しさというのは、“大王”と呼ばれる人間には皆あります。僕は中国ものをよく書くのですが、清の時代に乾隆帝(けんりゅうてい)というスーパーキングがいて、彼はどこまで領土を広げても飽き足らない人だった。ルイ14世もどれだけお金をかけても飽き足らずに、未完成だと言う。そのように考えるととても悲しい人物です。そういった王様だけが持つ究極の悲しさが、結局は庶民の間の誰にでも起こりうる親子の情愛や悲しさとぴったり一致してしまうというところが「王妃の館」の悲劇なのです。
田渕:あぁ! なるほど! 浅田先生とお話ができ、いいひらめきを与えていただきました。
北白川右京は浅田次郎氏の分身という面も!
——朝夏まなとが演じる作家の北白川右京役についてはいかがですか?
浅田:北白川右京は、僕と全くタイプの違う小説家ですが、分身のようなところもあります。小説というのは彼が考えているように一瞬でできるものなんですよ。どんなに長い小説も短い小説も時間は関係ない。一瞬で“降りて”くる感じです。小説の中に、右京が急に書き始めてバーッと原稿をばらまいて、それを編集者が拾って読む、というシーンがありますが、あの感じはありますね。
田渕:やはり分身なのですね。
浅田:どうでしょうか、誰でも自分のことはわからないですから(笑)。ただ、僕は地味でおとなしい小説家だと主張しているけれど、編集者に訊いてみれば「とんでもない!」と。
田渕:エッセイを拝読していると、確かに浅田先生は地味ではないと思ったりもします(笑)。

——最後にメッセージをお願いします。
浅田:“浅田次郎、タカラヅカデビュー”を前に、今から胸がワクワクしております。私のことは北白川右京のようだと想像しながらご観劇いただき(笑)、どうぞ楽しんでください。
田渕:お客様のために、そして出演者が生き生きと演じるために脚本を書くことを、いつも自分の課題としています。それに加えて今回は、浅田先生が制作発表会の席で、ご自分の小説が映像化、舞台化されるときのお気持ちを“娘を嫁に出す気持ち”とおっしゃったように、原作という大切なお嬢様をお預かりしているので、浅田先生のお言葉を胸に、良い作品に仕上げていきたいです。どうぞ皆様ご期待ください。
【プロフィール】
浅田次郎
1951年東京都生まれ。1995年『地下鉄(メトロ)に乗って』で吉川英治文学新人賞、1997年『鉄道員(ぽっぽや)』で直木賞、2000年『壬生義士伝』で柴田錬三郎賞、2006年『お腹召しませ』で中央公論文芸賞と司馬遼太郎賞を受賞するなど、数々の文学賞に輝く。2015年にはその功績を称えられ紫綬褒章を受章。著書に<天切り松 闇がたり>シリーズや『プリズンホテル』『蒼穹の昴』『シェエラザード』『憑神』『ま、いっか。』『ハッピー・リタイアメント』『降霊会の夜』『一路』など多数。
田渕大輔
大阪府出身。2006年宝塚歌劇団入団。2012年、ヴィクトリア朝時代のロンドンを舞台に奇術師の青年が巻き込まれる騒動を描いた、ウィットに富んだ作品『Victorian Jazz』(花組・バウホール)で演出家デビュー。2014年、フランス王アンリ4世が即位するまでの葛藤や妻を巡る愛をドラマティックに描いた『SANCTUARY』(宙組)を発表。2015年『相続人の肖像』(宙組)では父と決別状態にある主人公が、真実の愛を知り成長していく姿を瑞々しく描き出す。2016年、不朽の名作『ローマの休日』(雪組)のミュージカル化に成功。新聞記者と王女の束の間の恋を生き生きと綴り、感動的なラストへと導いた。今作が宝塚大劇場デビュー作となる。